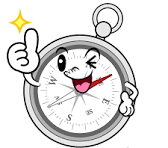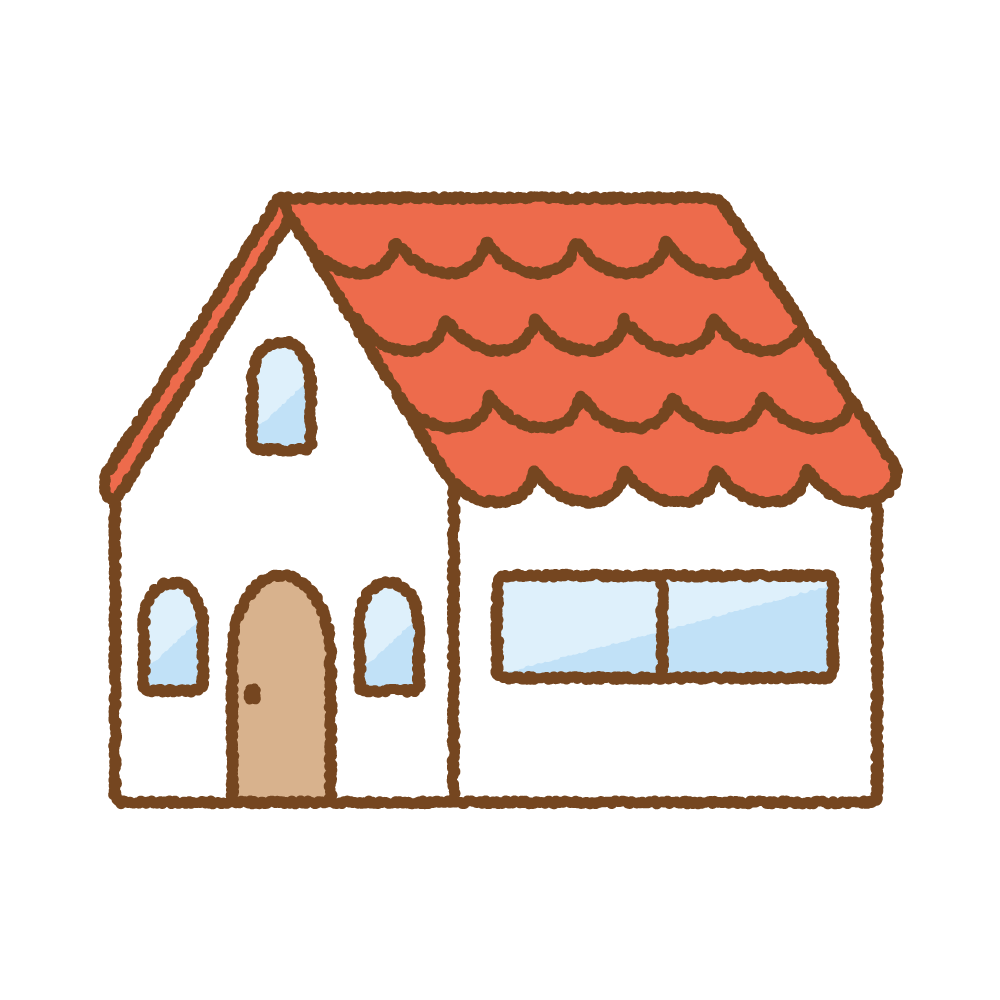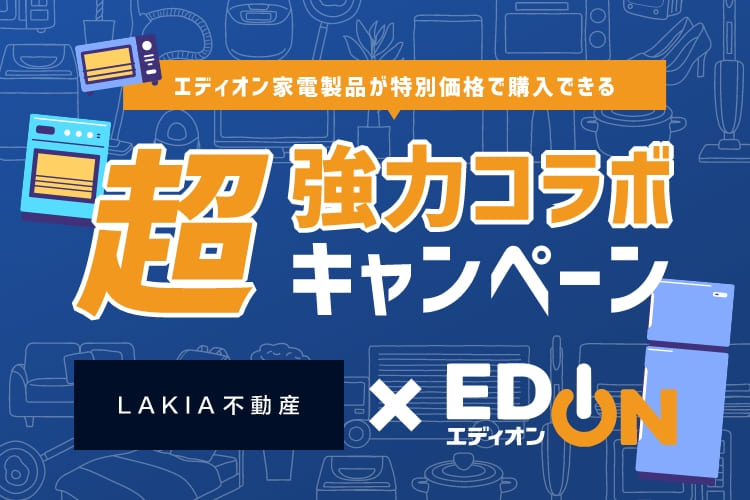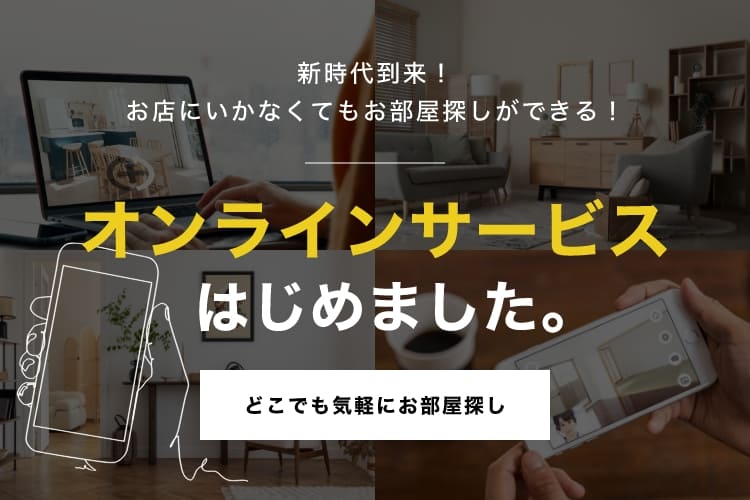「住みたい街ランキング」を見ながら、「次に引っ越すならこのエリアがいいかも!」とワクワクしたことはありませんか?
たしかに人気のエリアには魅力がたくさんあります。でも、実際に暮らしてみると「スーパーが遠い…」「保育園が全然空いてない」「通勤がしんどい…」なんてギャップを感じることも。
さらに、引っ越しはタイミングによって費用や選べる物件の数が大きく変わることをご存じですか?
このコラムでは、引っ越しが安くなる時期や、タイミングのコツにくわえて、物件選びの前に知っておきたい「エリア選びの7つの視点」をご紹介します。
「人気の街」だけに頼らず、自分たちのライフスタイルに合った街選びのヒントを、一緒に見つけていきましょう!
① なぜ人気の街が“暮らしやすい街”とは限らないのか?
「住みたい街ランキング」には、“イメージ”や“知名度”が大きく影響しています。たとえば、おしゃれなカフェが並ぶ街、再開発で注目を集めているエリアなどは話題になりやすい一方で、**実際に暮らしてみると「物価が高い」「混雑がすごい」「保育園に入れない」**などの現実が見えてくることも。
ランキングはあくまで「人気の傾向」。自分や家族にとって何が“暮らしやすい”のかを、生活動線や価値観に照らして考えることが、失敗しない街選びの第一歩です。
② 通勤時間・混雑率・駅力を見る
物件を探すとき、駅からの距離は多くの人が気にしますが、実はそれ以上に大切なのが「駅力」と「通勤の快適さ」です。たとえば同じ20分の通勤でも、直通か乗り換えがあるか、座れるかどうか、始発駅かどうかで毎日のストレスは大きく変わります。
さらに、都心に近い人気路線は混雑率が高く、毎日ぎゅうぎゅう…ということも。“駅力”=路線の本数、始発の有無、混雑具合なども含めてチェックしましょう。物件だけでなく「路線の性能」を見るのが、快適な暮らしのカギです
③ 保育園・病院・スーパーの「生活利便性指数」
子育て世帯や共働き家庭にとって、日々の生活が回るかどうかはとても重要です。徒歩圏内に保育園・小児科・スーパーが揃っているか。夜間・休日に対応できる病院があるか。保活の“激戦区”ではないか。「便利さ」は駅からの距離だけで測れません。
Googleマップで検索したり、自治体の子育て支援ページを見るだけでも、リアルな利便性が見えてきます。“便利に暮らせるか?”は、実際に1日住んで動いてみるイメージで確認するのがおすすめです。
④ ハザードマップと災害リスク
どんなに人気の街でも、災害リスクが高い場所では長く安心して住むことは難しくなります。近年はゲリラ豪雨や地震、台風などの自然災害が増加傾向にあり、「地盤の強さ」や「浸水リスク」は重要なチェックポイントです。
国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、洪水・土砂災害・高潮など、地域ごとの災害リスクを確認できます。不動産会社が積極的に教えてくれない情報こそ、自分で調べておくことが安心につながります。
⑤ 5年後に価値が下がらない街を見極めるには
「将来、もし売るなら」「資産価値としての安定性は?」と考える人にとっては、5年後・10年後に価値が下がりにくい街かどうかも大切な視点です。
チェックポイントは、再開発の計画、人口の増減、交通インフラの充実度、そして“住宅供給過多”ではないかどうか。分譲マンションの新築供給が多すぎるエリアは、将来的に価格が下がる傾向があります。
反対に、地価が安定しており、賃貸需要も高い場所は、資産としても安心。数字や計画をもとに、“今だけじゃない街”を選びましょう。
⑥ 地域の雰囲気は「夜に歩くと分かる」
日中に内見した物件が「良さそう」でも、夜になると雰囲気が一変するエリアもあります。街灯が少ない、人通りが極端に減る、騒がしい店舗がある…など、昼間だけでは見えない面が多いのです。
また、地域住民の様子や雰囲気(挨拶する?静か?子どもが多い?)も、実際に歩くことでしか分かりません。候補地が決まったら、平日夜・土日昼と複数のタイミングで歩いてみると、暮らしのイメージがぐっと具体的になります。
⑦ まとめ:駅近だけが正解じゃない
「駅徒歩〇分」や「有名エリア」といった分かりやすい条件は魅力的ですが、本当に暮らしやすい街は、人によって違います。
家族構成、ライフスタイル、仕事のスタイル、価値観…。それぞれの“暮らしの軸”をもとに街を選ぶことで、住んでからの満足度は大きく変わります。
エリア選びに正解はありません。けれど、“自分たちに合った街”を見つけるための視点を持てば、ランキングや広告に惑わされない、後悔しない家探しができるはずです。












 で連絡する
で連絡する